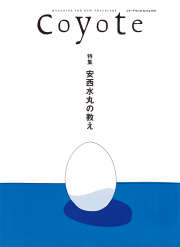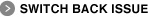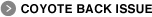音楽が終わったら

音楽を聴くという行為は、インターネットとそれにまつわる様々なサービスの普及、進歩により、ますます手軽に、カジュアルなものとなってきている。何か気になる曲や聴きたい曲があれば、大抵のものはネットで検索すれば即座に、簡単に、しかも時には無料でそれを聴くことができる。ひと昔前と比べれば、音楽好きにとってそれは夢のような時代と呼べるだろう。
けれどその一方であるミュージシャンもインタビューで指摘するように、音楽が消費されるスピードが年々加速していく傾向にあるのも確かだ。日々膨大な数の音楽が生まれ、そしてその多くはあっという間に消費され、過去のものとなる。誰もが手軽に新しい音楽にアクセスし、その手軽さゆえにその行為は日常化し、かつては特別な<体験>だったそれは、ごくありふれた日々の暮らしの中に埋もれていく――。だからこそ音楽の作り手たちは皆、それでもリスナーにとってその音楽との出会いが特別な体験となり得るよう、自らの作品を精魂込めて作り上げていく。
初めて自分自身で手に入れたレコードやCDを、胸を高ぶらせながらもどかしい気持ちでパッケージを開き、プレーヤーにセットする。最初の一音が鳴り始めるその瞬間の高揚感。たとえ音楽がパッケージメディアでなくなったとしても、その感覚はやはり変わらないだろう。ターンテーブルの上のレコードに針を下ろすこと、CDプレーヤーの再生ボタンを押すこと、PCのマウスをクリックすること、スマートフォンのディスプレイにタッチすること。違いはその動作だけだ。そしてその音楽が終わった時、心に何かが残される。きっと特別な何かが。
「SWITCH」Vol.32 No.4(福山雅治 今を生きる、今を歌う)
- Posted on 2014/03/20